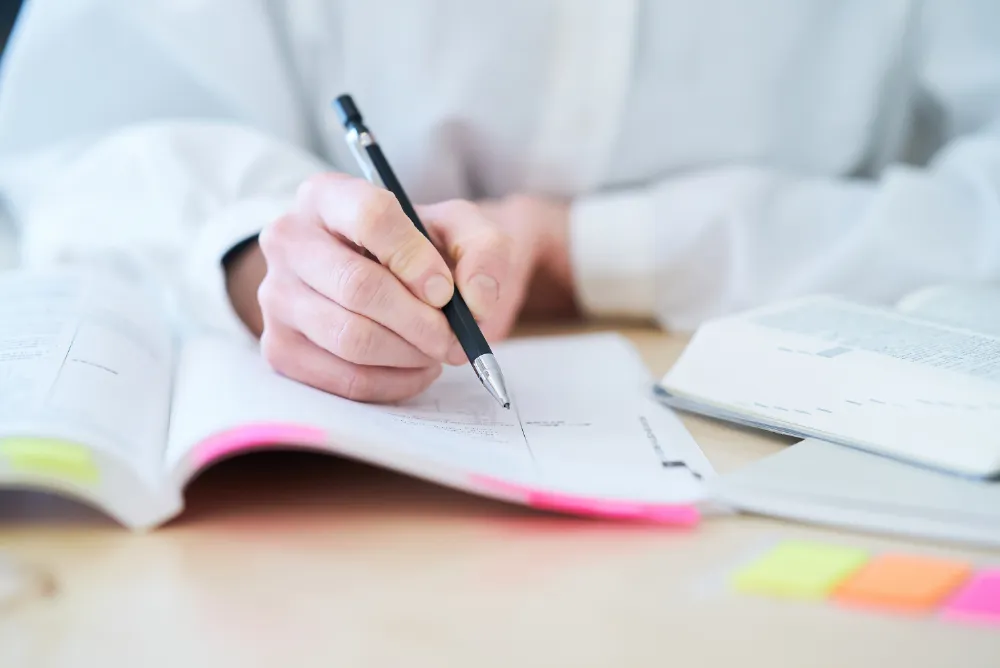この記事では、手洗いがやめられない原因や心理の背景、克服する方法について解説します。
手洗いがやめられないのは強迫性障害のサイン?
「汚れが気になっても何度も手を洗う」「手を洗わないと不安で落ち着かない」といったことで生活に支障をきたしている場合、強迫性障害に該当する状態だと言えます。
強迫性障害は自分で「やりすぎだ」と分かっていても、不安のために何度も繰り返し特定の行為を行ってしまう病気です。
強迫性障害の特徴
強迫性障害は、発症が20歳前後で男性は女性に比べて発症年齢が低いケースが多いです。
発症しても周りの人に悩みを言わないため、病院やカウンセリングルームに相談に行くのは30歳前後になりやすい傾向があります。
時折、学生の方から相談を受けることはありますが、ご両親が手洗いをやめられない状態やその他の行為に気付いた場合がほとんどです。
強迫行為は広がっていきやすく、手洗いからスタートして、鍵が締まったかどうか繰り返し確認する、間違ったことを言ったことを考えて何度も言い直す等の問題を抱えることがあります。
手以外のところが汚いと思い始め、外出した後の服、椅子、床などと消毒する範囲が広がっていくケースもありますね。
今の状態ならなんとか耐えられるからと我慢するのはやめましょう。
手洗いがやめられないことで生活に支障をきたしていない段階でも改善に向けた行動を起こしていただければと考えております。
強迫行為を隠すことによるリスク
強迫性障害の人は、自分の行動が「普通ではない」と認識していることが多いため、家族や友人に相談できず、一人で考え込んでしまう傾向があります。
しかし、行為を隠し続けることで、次のような悪循環に陥ってしまいます。
- 不安を解消するために手を洗う
- 一時的に安心するがすぐにまた不安が襲ってくる
- さらに手洗いの頻度が増える
この状態が続くと、「外出できない」「他の人と関わるのが怖い」といった深刻な問題に発展していく可能性が十分にあります。
手洗いをやめられない原因
心の葛藤を避けたい心理
手洗いがやめられない背景には、「心の葛藤を避けたい」という無意識の心理があります。
背景に以下のような問題を抱えているケースが多いです。
- 完璧主義で真面目な性格
- 親子関係の問題
- いじめや対人関係のストレス
手を洗うことに対しても過剰だと自分でわかっているため、手を洗わなくていいはずなのに洗ってしまうという葛藤が生じています。
脳の神経回路の異常
強迫性障害は、脳の神経回路や情報伝達に異常が生じている可能性が指摘されています。
「手洗いをやめたい」と思っても、脳が「手を洗わなければ不安が解消されない」と指示を出し続けるため、やめられなくなってしまうのです。
神経細胞の末端でセロトニンの分泌量が増えると強迫症状が和らぐと言われています。
手洗いがやめられない強迫性障害の克服方法
不安が収まるまで待つ
強迫性障害は不安に対して脳が過剰反応している状態なので、その反応が収まるまで待つ経験を積むことが改善に必要です。
不安だからと手を洗うことを繰り返せば行為は強化され、どんどん悪化していきます。
逆に不安でも手を洗わず置いておく、不安が収まるまで待つことができればできるほど手を洗う行為は収まっていきます。
ただ、手を洗わないようにするというのは非常に難しいため、カウンセリングを受けながら行為を止めるための工夫をしていくのが現実的かと思います。
認知の歪みを修正する
手を洗わないと大変なことになるという思考が影響しているため、手を洗わなくても大丈夫だという思考に変えていくことが有効です。
認知行動療法の一つである曝露反応妨害法では、実際に汚いと思う物を段階的に触るようにしていき、手を洗わなくても問題が起こらないことを経験していきます。
汚いと思う物に触れることは抵抗を感じるため、抵抗が小さいことから少しずつ取り組んでいくことが必要です。
カウンセリングを受ける
強迫性障害のような潜在的な葛藤を抱えている方は、カウンセリングを受けて自分の心の中で葛藤に気づき、それを受け入れることによって気持ちが楽になります。
また、カウンセラーから強迫性障害についての知識を学ぶことは改善のために有効です。
カウンセリングでは、話を聞きながらどういうアプローチがその人の悩みの改善に適しているか考えながら質問やアドバイスをするのですが、相談に来ていただければ担当のカウンセラーがしっかりと話をお聞きして、その内容をもとに改善のご提案をさせていただきます。