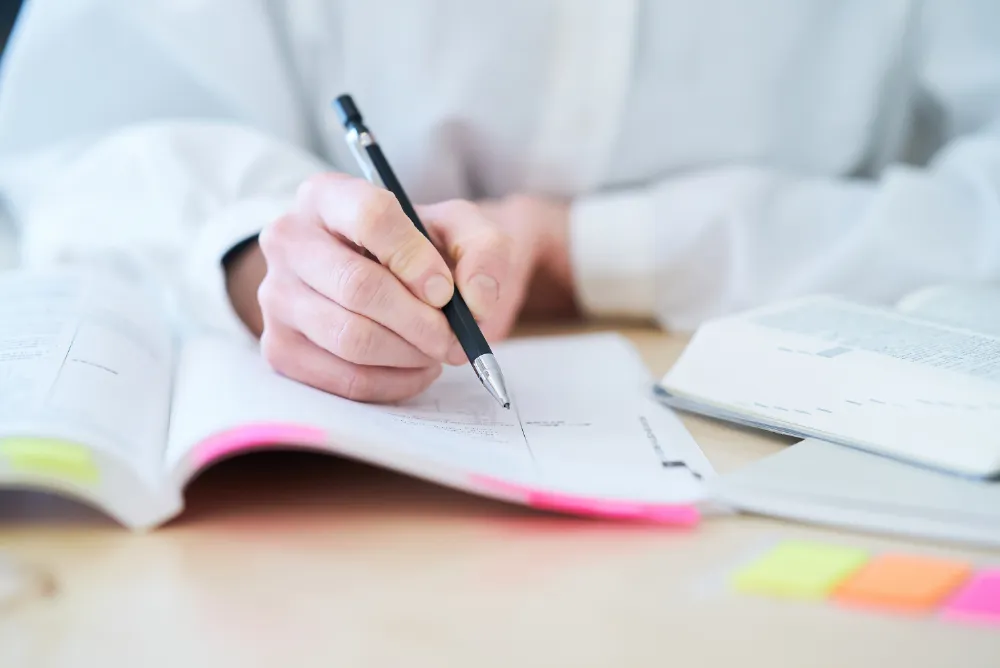カウンセリングへの依存に関する質問
カウンセリングに依存してしまうということはありませんか?
カウンセリングを受けたいとは思っているけど、カウンセリング自体に依存してしまうことはないだろうかと心配している方もおられるようです。
まず、カウンセリングへの依存とはどんな状態なのか、その定義については以下のようにご理解いただければいいかと思います。
カウンセリングを利用する本来の目的には、自己理解、問題解決、心の安定などなどがありますが、「カウンセラーに会わないと不安」「カウンセラーの答えが欲しい」といった状態になり、カウンセリングそのものが“心の支え”になってしまっている状態です。
おそらく、カウンセリングに依存してしまうことがないだろうか心配されている方は、カウンセラーに相談しないと不安になる、自分のことを自分で決めることができなくなるという状態になってしまうことを懸念されているのではないかと思います。
その結果として、いつまでも自分で自分の問題に向き合う力がつかない、時間とお金を必要以上にカウンセリングに掛けてしまうということも考えられるため、カウンセリングを受けると依存してしまうのではないか考えてしまうのではないでしょうか。
カウンセリングに依存する理由
・カウンセリングによる共感、受容に頼りすぎる
カウンセラーはクライエントに共感的かつ重要的な態度で話を聴くため、「自分を無条件に受け入れてくれる存在」と感じやすく、カウンセリングによる共感と受容だけを心の支えにしてしまうと依存しやすくなります。・ 日常の孤独や支えの欠如
周囲に話せる人がいない、理解してもらえない環境にいる場合、カウンセリングが唯一の拠り所になって、「カウンセラーだけが自分をわかってくれる」という気持ちになると依存しやすくなります。・ 問題解決の主導権をセラピストに委ねてしまう
自分で考えること、自分で決めことを放棄して「カウンセラーに聞いてから決める」というような発想でカウンセリングを利用すると依存に陥りやすいと言えます。要注意!クライエントを依存させやすいカウンセラー
下記のようなカウンセラーは意識的、無意識的にクライエントを依存させてしまうので要注意です。 特にピンクで強要している点が問題です。・ カウンセリングのルールを守らない
「いつでも相談に乗る」といい、決められた場所、時間以外でクライエントにあることを提案する、このようなことを提案する。・ 自分だけが味方だと思わせようとする
話しの詳細も確認せずにただ共感と受容だけを行い、クライエントの家族や友人、パートナーなどを否定して自分だけが理解者であるというような発言をする。・ 自分だけに相談させようとする
自分のアドバイスだけを聴くこと、他のカウンセリングルームや病院に通わないことを求めてくる。必要以上に多くのカウンセリングルームや病院に行く、問題のあるカウンセラーや医者に相談するということは望ましくないので、適切な理由で通わないよう提案することはありますが、「自分だけ」に相談するように求めるカウンセラーは望ましくありません。
・ 短期間に何度も通わせようとする
クライエントが不安になるようなことを言って短期間に何度もカウンセリングを受けることを提案する。間隔を詰めてきた方が良いケースもあるが、不安をあおるようなことを言うことは良くありません。
・ 自分だけが味方だと思わせようとする
話しの詳細も確認せずにただ共感と受容だけを行い、クライエントの家族や友人、パートナーなどを否定してカウンセリングへの依存を防止する方針
当社では、クライエントがカウンセリングに依存しないよう明確なカウンセリング利用のルールを設けていたり、カウンセリングを受ける感覚を必要以上に短くしないように促しています。カウンセリングのルールの明確化
カウンセリングへの依存を防ぐために大切なのは、カウンセリングを利用してもらう際のルールの明確化を行うことです。
カウンセリングの時間以外に相談を受け付けない、決められた場所や方法でのみ相談を受け付けるといったルールに従って利用していただくことがい大切で、カウンセラーもそのルールから外れた支援を行ないことを徹底することが依存を防ぐことにつながります。
カウンセリング利用の間隔
カウンセラーが適度なカウンセリングの間隔を提案することも心掛けています。
相談内容によってどれくらいの期間を空けて次のカウンセリングを受けた方が良いのかは変わってきますが、クライエントの要望を踏まえつつ望まし感覚を提案することが依存を防ぐことにつながると考えています。
相談内容やクライエントの状態によっては、次の5日~10日以内の短い間隔を提案することもありますが、多くは月1回程度の頻度から開始して、少しずつ間隔を空けながらカウンセリングを受けなくても大丈夫な期間を延ばしていくことが多いです。
また数回のカウンセリングだけで問題の解決が進んだ場合は、過度に通うことを提案することなくカウンセリングを卒業していただくケースもあり、依存にならないカウンセリングのご利用を提案しています。
カウンセリングによって悩む力を養い問題解決能力を高める
人生は悩むことなく生きていくことは難しく、誰かに悩みを解決してもらえることばかりではありません。
カウンセリングは、カウンセラーがクライエントの悩みを解決することではなく、クライエント自身が自分の悩みを解決するために正しく悩むことをサポートするものだということをAXIAのカウンセラーは大切にしています。
カウンセラーは悩みを聴くことはできても、クライエントに変わって悩みの解決のために行動できるわけではありません。
ただ、悩みというものは悩み方を間違ってしまうと深くなり、解決が難しくなってしまいます。
カウンセリングは、正しく悩む力を育む時間であり、カウンセラーは正しく悩む力が向上するように話を聴き、質問をしていくのです。
カウンセラーからの質問が自分への問い掛けに変わる
カウンセリングの中では、カウンセラーが話を聴きつつ、クライエントに対して質 問をしていきますが、その質問はクライエントの悩みについて正しい情報を得るという目的だけでなく、クライエントの認知や思考が悩みの解決に向かうための問い掛けが目的になっていることもあります。
人間は、心の中でさまざまな問い掛けを自分に向け、その上で自分の行動を選択しています。
この問い掛けによっては、悩みが解決しにくい行動を取ってしまうこともあります。
カウンセリングに来られている方は、少なからず自分への問い掛けが悩みの解決を妨げている傾向があるので、カウンセラーは質問によってクライエントの心の中で行われる自分への問い掛けの方向を適切なものに導いてい行きます。
そのようなやり取りを繰り返えすことによって、クライエントがカウンセラーに相談をしなくても自分の悩みを解決する問い掛けを行えるようになって行くので少しずつカウンセリングから離れていくことができるのです。
AXIAのカウンセラーは、クライエントの自立を促し、生きるために必要な悩む力を高める時間だという意識を持ってカウンセリングをしていますので、悩みが深い時に一時的にカウンセリングに依存することはあっても、そこから自立していくようにカウンセリングを進めていくのでご安心下さい。